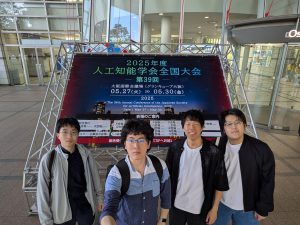2025年5月27日~5月30日に大阪国際会議場(グランキューブ大阪)/オンライン(ハイブリット)にて開催された「2025年度 人工知能学会全国大会(第39回)」に本研究室より、鎌田 理久さん(修士2年)、上前 諒輔さん(修士2年)、野村 爽太さん(修士2年)、帆井 健悟さん(修士1年)、が参加し、研究発表を行いました。
[2025年度 人工知能学会全国大会 (第39回)]◆ 鎌田 理久, 横山 想一郎, 山下 倫央, 川村 秀憲: 路面画像と気象情報に基づく L1 正則化を活用した除雪出動予測, https://doi.org/10.11517/pjsai.JSAI2025.0_2O1GS1002
積雪地帯における冬期の道路除雪業務は,道路交通や生活インフラを維持するうえで欠かせない.
しかし,除雪出動の判断は気象や道路状況の変化に大きく左右されるため,担当者が下した判断が覆る場合もしばしば発生し,除雪作業員に不確実な出動への備えを強いるだけでなく,担当者にも心理的負荷を与えている.
本研究では,この課題を解決するために,路面画像と多様な気象情報を統合し,L1正則化による特徴量選択を活用した除雪出動予測手法を提案する.
具体的には,1時間単位の気温や降雪量,風向といった質的・量的データを含む膨大な候補から,モデル学習に有効な特徴量を自動的に選択することで,高精度な予測を可能にする.
実験では,担当者の判断や従来のロジスティック回帰モデルと比較して,本手法がより高い予測精度を示すことを確認した.
◆ 上前 諒輔, 横山 想一郎, 山下 倫央, 川村 秀憲, 永田 功 : 大規模言語モデルを用いたマニュアル向け文章の分類および順序付け手法の提案, https://doi.org/10.11517/pjsai.JSAI2025.0_4A1GS1004
マニュアルの作成において、利用者が必要な情報を円滑に探索できる目次構成を設計することは重要である。
しかし、利用者の視点に基づく目次構成を構築するには、目次作成に関する専門知識が求められるため容易ではない。
本研究では、この課題を解決するために大規模言語モデルを用いた目次構成の自動生成手法を提案する。具体的には、マニュアル作成の専門家が活用するルールや知識を含むプロンプトを設計することで、利用者が情報を検索しやすい目次構成を生成する。
実際のマニュアルを対象に、提案手法によって生成した目次構成と既存の目次構成を比較し、専門家が作成した目次構成と同等の構成が得られることを確認した。
また、本論文における実験を通じて、汎用的な目次構成を自動生成する手法の考察とさらなる改善点を議論する。
◆ 野村 爽太, 横山 想一郎, 山下 倫央, 川村 秀憲, 大原 美保 : 深層言語モデルを用いた災害対応検証報告書からのヒヤリハット事例文の分類手法の提案, https://doi.org/10.11517/pjsai.JSAI2025.0_4A1GS1005
近年,多発する災害への対応力向上のため,自治体による災害対応検証報告書の活用が進んでいる.
これらの報告書には,行政職員が遭遇したヒヤリハット事例が記録されており,その収集と分類は防災対策の向上に不可欠である.
現在の事例抽出は手作業で行われており,状況に基づいて12種類のクラスに分類されている.
ただし,2017年以降の水害関連の検証報告書に限定しても,85点・全7,053ページあり,人手による抽出・分類が困難になってきており,ヒヤリハット事例の抽出・分類を支援するツールが望まれる.
これまでの我々の研究では,深層学習モデルBERTを用いたヒヤリハット事例文の抽出手法を提案し,高精度で抽出が可能だと確認した.
本研究では,深層学習モデルBERTを用いて抽出したヒヤリハット事例文を12クラスに分類する手法を提案する.
モデルの学習には人手で抽出・分類されたヒヤリハット事例を学習データとして用いている.
Top-3 accuracy を用いたヒヤリハット事例文分類手法の評価実験では,データ数の少ないクラスの正解率が低い傾向は見られたが,データ数の多いクラスの正解率は実用可能なレベルにあることが確認された.
◆ 帆井 健悟, 横山 想一郎, 山下 倫央, 川村 秀憲, 加太 宏明, 柏村 聡 : アダプティブクルーズコントロールにおけるステレオカメラを用いた深層ニューラルネットワークの評価, https://doi.org/10.11517/pjsai.JSAI2025.0_3M1GS1003
近年エンドツーエンド型の自動運転システムの研究が盛んであるが,高精度な推論には高性能の学習用・推論用マシンが必要であり,研究開発や商業展開の大きな負担となっている.
これはステレオカメラを入力センサとして用いることで対処できる可能性がある.
アルゴリズムでの測距によりネットワーク内での測距を省略でき,単一センサでの画像と距離情報の取得によりセンサフュージョンが不要になる可能性があり,モデルの簡素化が期待できる.
本研究では,ステレオカメラを用いた自動運転のエンドツーエンドモデルの初期検討として,基礎的なタスクであるアダプティブクルーズコントロールを行うモデルを開発する.
既存モデルであるTransfuserを基に,ステレオカメラで取得した情報を用いて自車の加速度の予測を行うネットワークへ改変することで,これを実現する.
日本の公道の約16万フレームのデータを用いて学習・評価した結果,加減速が少ない単調な環境では良好な精度が得られ,ステレオカメラモデルの実用化可能性が示唆された.
一方,大きな加減速,上り坂,急激な光変化では精度が低下することが確認され,原因を考察し改善策を提案した.
研究内容にご興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ: http://harmo-lab.jp/contact